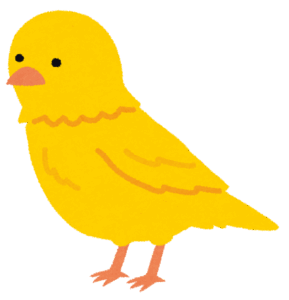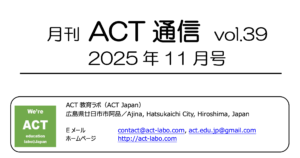あじなんだより Ajinan Report vol.38
ACT教育ラボの所在地は広島県西部にある廿日市市阿品(「はつかいちし・あじな」と読みます)。「あじな」の住民になった自らを「あじなん」と名づけ、暮らしの中で気づいたこと・感じたことを報告していきます。今回のお題は、道端で見上げると大抵そこにいるあいつーー“カラス”を眺めながらのとりとめのない(毎度おなじみ!)雑感です。

今年の炎暑の中、電柱にとまるカラスを見上げて、ふと「熱中症にならないのかな?」と不思議に思ったのですが、ネット検索では「なる」という説と「ならない」という説が見つかり、「ならない」派がやや優勢。カラスの黒い体色は熱を吸収しやすい反面、放出するのにも優れているからという根拠には説得力があるものの、朝から30°Cを超える強烈な日差しを体感すると、今後はカラスも従来通りの生活習慣では立ちいかないような気がします。そのうち夜行性のカラスが登場するかもしれませんね。「なる」派は、「飛んでいる最中に熱中症で落ちてくる個体もいる」と言っていますが、それは超まれなケースではないかなあ。
阿品対岸の宮島では真夏にカラスが川で水浴びをしているのをよく見かけます。熱中症対策でしょうか。私なんぞは「これぞ“カラスの行水”だ〜」と喜んで写真に収めたりしていますが、観光客の関心は全く向かないようで。世界中に生息し、そのどこでも結構迷惑がられていることが察せられます。うちの町内でも生ゴミ出しの日には対カラスバトルが繰り広げられるし。


しかし宮島におけるカラスは、単なる厄介者ではありません。厳島神社の神様のお使いは、島のあっちこっちで愛嬌を振りまいているシカではなく、このカラスなのです。創建由来によると、九州からやってきた女神様が宮島の対岸に住む某豪族の夢枕に立ち、「この島に鎮座したいのじゃ」と告げたそう。某氏が「神社は建てますけど、この島のどこらへんがご希望ですか?」と尋ねると、姫神様は「カラスを遣わすから、それが案内する場所に建ててちょうだい」と。
そこで島の沿岸に船を浮かべたものの、なかなかカラスが現れなかったので、団子を作ってみたところ、ようやくオスメス一対のカラスが登場。団子をついばんだその二羽のカラスの導きで現在社殿が建てられている土地が選ばれたとの言い伝えがあります。この伝説にちなんで、今でも宮島町内では「御鳥喰式(おとぐいしき)」という、カラスに団子を食べさせる神事を年に一回氏子中で取り行っています。儀式の際に滞りなく団子をついばんでもらうため、カラスを餌付けをしていることは神様にはナイショにしておきましょう(とっくにお見通しかな)。
話変わって。カラス、ホトトギス、ウグイスの「ス」は古語で鳥を表す接尾辞だと言われています。では「カ」と「ラ」は何かといえば、鳴き声ではないかという説が有力。カラスの鳴き声に耳を澄ましてみると、確かにカー音に少々のど声のラー音が混じっているような…。英語でクロウcrow、フランス語でコルボーcorbeau、ドイツ語クレーエKrähe、イタリア語コルボcorvoと、カ行音にラ行音が続くのを知ると、鳴き声説の信ぴょう性が高まります。もっとも中国語ではウーヤーwuya(烏鴉)、マレー語ではガガックgagakと鳴く(聞こえる?)みたいですが。