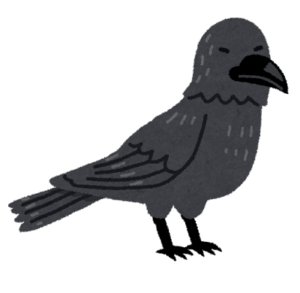さくぶん道場 第199回 大谷雅憲
坑内カナリア芸術論
カート・ヴォネガットの「坑内カナリア芸術論」を知ったのは、大江健三郎のエッセイを通してだった。まだ、ヴォネガットの作品を知る前だったので、たぶん、高校生のときだろう。ヴォネガットの作品をすべて読んだ後、『ヴォネガット、大いに語る』(ハヤカワ文庫)読むと、いろんなことが腑に落ちた。
「(芸術の効用について)わたしが思いつく最も肯定的な理念は、<坑内カナリア芸術論>と勝手に名づけているものです。芸術家は非常に感受性が強いからこそ社会にとって有用だ、という理論です。彼らは超高感度ですから、有毒ガスが充満している坑内のカナリアよろしく、より屈強な人々が多少とも危険を察知するずっと前に気絶してしまいます。」
「きょうこの会(アメリカ物理学会)でわたしにできる最善のことは、気絶することかもしれません。ところが、芸術家は毎日何千人も気絶しているのに、だれも全然注意を払ってくれないようです。」

ヴォネガットの創作動機は「文明への嫌悪」に貫かれていた。彼の小説に登場する悪玉は、個人ではなくて文化、社会、歴史。彼の主張は一貫していた。「人に親切にしなさい」「人間は孤立に耐えられるようにはできていない。わたしたちに必要なのは、新しい部族社会だ」。この二つに尽きる。彼は愛を信じていなかった。愛は、憎悪と排除を生み出すから。でも親切だったら誰にだってできる。「愛は負けても、親切は勝つ!」。まったくもって仰るとおり。人間にとって耐えられないのは、愛されないことではなくて、親切にできる相手を持たないことではないか。猫と一緒に暮らし、植物の世話をするようになって、わかったことだ。嘘だと思うなら、猫(犬でも亀でもいいです)と一緒に暮らし、植物の世話をしてみるといい。自分がいかにお節介で世話焼き人間であるかを知って驚くだろう。
文明への嫌悪は僕の中にも深く根ざしている。理由ははっきりしている。僕の遊び場をすべて壊してしまったから。子どもにとっての遊び場を馬鹿にしちゃいけない。それは、子どもにとって世界そのものであるし、大人にとって魂のふるさとだから。あの川とポンコツ山と池と池のそばにあった洞穴と秘密の基地と空き地のペンペン草と底無し沼と石崖にあったヘビ苺などなど。いつ誰がそれらのものと文明とを交換してくれなどと頼んだ?
それらのものが失われたとき、僕は魂のふるさとを失った。僕は僕の魂のふるさとを自分で創り出すしかなかった。小説や詩や音楽や絵画や哲学や神話や民話の力を借りて。
「インスピレーションの源は、疾病ではなく除け者にされたという現実、または幻想である。」
「詩人のクリストファー・クリストファーソンの言葉を引用しよう――『自由の別名は、失うものがないことだ』。除け者にされた才能ある人間の強みは、この言葉に要約されている。失うものがない人びとは、自由な気分で自分の考えをつらぬける。まわりの連中の考えをまねても、なんの得にもならないからだ。絶望は独創の母。」
「そして、独創の三人の美しい娘、すなわち絶望の孫娘たちは、この詩文集が実証したように、希望と、他者への感謝と、不動の自尊心である。」『死よりも悪い運命』(ハヤカワ文庫)
ヴォネガットが故郷のインディアナポリスで講演するはずだった講演録がある。これはヴォネガットによって話されることはなかった。講演の予定は2007年4月27日。ヴォネガットはその年の4月11日に自宅の階段で転倒して頭部を強打し、この世からバイバイした。何という間抜けな! 息子のマーク・ヴォネガットが代読した。ヴォネガットからの最後のメッセージはこれだ。
「さて、この終末の時代に、われわれはどんなふうに行動すればよいのか? もちろん、おたがいに対してとびきり親切であるべきです。しかし、それと同時に、あまり真剣にならないようにも心がけるべきでしょう。ジョークでうんと気が休まります。それと犬を飼うこと。もしすでに飼っておられなければね。わたしもつい先日から犬を飼いはじめましたが、新しい雑種です。フレンチ・プードルの血が半分と、中国のシーズーの血が半分。つまり、くそ・うんち(シット・プー)です。どうもご静聴ありがとう。それじゃ。」『追憶のハルマゲドン』(早川書房)
本当に、口の減らない親父さんだな。
「父が最後に書いたスピーチ原稿の最後のひとことは、父にとってどんなさよならをいうよりもいい方法だった」と息子のマークは書いている。本当にそうだ。ヴォネガットにぴったりだと思う。