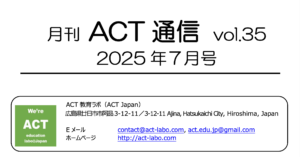さくぶん道場 第196回 大谷雅憲
猫の墓
6月10日、長い間やってなかった宿題をやっと片づけることができました。
ささやかな「猫の墓」を庭にあった材料で作りました。ここには今、マレーシアから持ってきた4ひきの猫たちが眠っています。

2008 年のある夜、エメラルドグリーンの目をしたキジトラの猫(ヒ メ)と路上で運命の出会いをしてから次々と猫たちを迎えること になり、最大で6匹の猫たちとの同居生活をしていました。
雨の日に母親とはぐれたらしい 300gの茶トラ(サン)。犬かカラスに襲われたのか首から背中にかけて膿が溜まっているのにガードハウスの前で気丈に話しかけてきた薄墨と白のマヤー。激しいスコールの後、木の虚に挟まったまま動けなくなっていた三毛(くう)。ガードハウスから連絡があって見にいくと下半身不随で、病院では安楽死を勧められ、だったら家で最後を見取ろうと連れて帰り、しばらくすると元気になった白黒デビルマン(チキ)。常連だった近所のパブのオーナーが代わり、そこに居着いていた猫を新しいオーナーに捨ててこいと言われて、困ったスタッフが連絡してきて引き取ることになったおばあちゃん(ドゥル)。
マレーシアにいるときに4ひきは亡くなりました。2022 年7月に日本に帰国が決まり、残りの2ひきの猫(くう・チキ)と 4 つの遺骨壷は飛行機とレンタカーの長旅の末、広島の海沿いの町にやってきました。
長い間放置されていた庭は、木の根や雑草や落ち葉などで荒れていました。庭の土を掘り返し、密集した根や球根を取り除き、雑草を抜き、石や砂利をふるいにかけ、土と落ち葉と米ぬかを混ぜて堆肥にし、なんとか庭が落ち着いたのが今年の6月。やっと「猫の墓」作りに取りかかる気になったというわけです。
「猫の墓」といえば、夏目漱石にも同名のエッセイがあります。『吾輩は猫である』のモデルになった猫(名前はない)が亡くなった時に書いたものです。漱石が猫好きであったかどうかは研究者にとっても不明のようですが、それでも、数人の知人には「死亡通知」を書いて送ったようです。それによると、車屋に頼んで箱詰めにして、裏庭の桜の木の下に埋め、白木の角材に「猫の墓」と記したとあります。その時に作った俳句も残っています。
この下に稲妻起こる宵あらん
何のことだかわかりません。漱石の弟子たちは律儀なやりとりをしています。
松根東洋城から高浜虚子への電報 先生の猫が死にたる寒さかな
高浜虚子の返電 吾輩の戒名もなき薄かな
そのほか、鈴木三重吉の俳句が一句、寺田寅彦は三句残っています。

三毛のくうは15歳、白黒のチキは11歳になりました。冬の寒 さにもなんとか適応できています(文句タラタラですが)。7月 21 日で日本に来て丸3年になります。