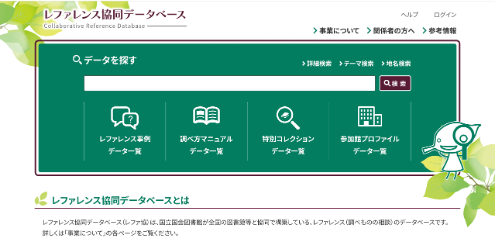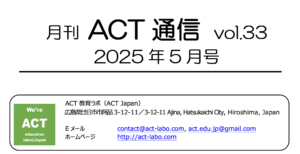あじなんだより Ajinan Report Vol.33
ACT教育ラボの所在地は広島県西部にある廿日市市阿品(「はつかいちし・あじな」と読みます)。「あじな」の住民になった自らを「あじなん」と名づけ、暮らしの中で気づいたこと・感じたことを報告していきます。今回は、町内会についてのあれこれ+@。わが「鼓ヶ浜」町内会は“つづみ”ではなく、なぜか“つつみ”と読ませます。
町内会の役員に選出されました。というと、まるで“役員に立候補して選挙運動の末に投票多数で当選した”みたいな感じですが、さにあらず。ご近所の前任者から玄関先で、「次年度の総務を引き受けてくれませんか」と頼まれて、たいして深く考えずに「いいっすよ」と答え、先日の町内会総会で拍手をもって承認されたという次第です。
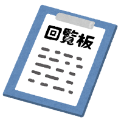
しかし町内会と聞くと、とっさに「なんだかめんどくさそう」と思ってしまうのは私だけではないのではないでしょうか(言い回しがくどい)。戦時中の(私はまだ生まれてませんよ。念のため)、隣組で互いを見張り合い、地域のオキテを破る者は村八分にされる、的な息苦しいイメージが浮かびます。最近では、神戸で町内会に入らない家庭のゴミ出し拒否問題が最高裁まで争っているニュースもありますしね。

ではなぜ役員を引き受けたのかといえば、単純に「断るのもめんどうだった」と言いましょうか、「どうせそのうち回ってくるのは自明」と言いましょうか。それに”町内会”を”自治会”に言い換えてみると、あら不思議! 封建制の残滓たる家父長的な組織ではなく、民主主義の基本ユニットのように思えてくるではないですか。そう考えると、地域コミュニティに積極的に関わろうという意欲がわかなくもない。
この町は約半世紀前に瀬戸内海の一部を埋め立てて作られた住宅地で、初代の入居者が80〜90代となり、どんどん代替わりが進んでいます。しばらく空き家だった場所には新しい家やアパートが建ち、新しい住人も入ってきています。こうした、さまざまな年代のさまざまな考え方の人たちが一つの町で気持ちよく暮らすにはどうしたらいいのかを考えるのは、ちょっとおもしろいかもと思いはじめました。ま、そうは言っても総務の主たる仕事は町内会費を集めることぐらいですけども。 [ご町内より宮島を臨む夕景→]


今回の記事を書くにあたって町内会の起源や定義を知りたいと思い、『レファレンス協同データベース(通称:レファ協)』を利用しました。この無料で使えるデータベースはすごいです。国立国会図書館が全国の図書館と連携して利用者から寄せられたさまざまな疑問に答えているのですが、各地の図書館職員の方々が参考文献を教えてくれるだけでなく、ややこしい文書を読んだ上でそれをかみくだいてわかりやすい回答を出してくれます。しかも本に関する質問だけに答えるのではない。
たとえば、音楽認識ソフトがまだ存在していない2013年、牛久市立図書館に小5男子が「セブンイレブンに入ると流れている曲の入ったCDはあるか」とたずねています。それに応えて職員が思い当たるメロディを口ずさんで質問者に「この曲?」と確認。そこから歌詞の手がかりを得て、Google検索で曲名を同定、そのうえで蔵書検索、と進んでいる。結果は「曲名はザ・タイマーズのデイドリーム・ビリーバーと判明。当館にはザ・タイマーズ版はなく、モンキーズ版の所蔵はあり」となっています。小5男子、貸し出してもらったかなあ…。