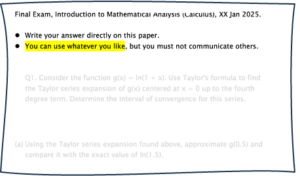さくぶん道場 第192回 大谷雅憲
なぜ、「花は桜」なのか
桜の花がいつ日本文化の中心になったか
日本では特に説明がない場合、「花」といえば「桜」を指す。これは古典の授業で教わった。四季折々の自然の移ろいに人生を重ね合わせてきた日本人にとって、花と月は日本人の自然の好みだけでなく、美意識や倫理観の根底にあるものを象徴してきた。数ある花の中で、なぜ桜が花の代名詞の位置を占めるようになったのか。それがわかれば日本文化と呼ばれるものの典型が見えてくるかもしれない。
もっとも、純粋な日本文化などというものが存在するわけではない。花の愛し方も中国からの影響によるものだ。ならば、外国からの文化が日本やってきたときに、何が残り、何が失われたのか。また受容の過程でどのように変容してきたのかを考えると、日本文化の特色が浮かび上がってくるような気がする。
中国で好まれた花木は「桃李梅杏」だった。この中に桜は入っていない。また、「花」という語がどれか特定の花の名前を指すこともなかった。ただ、中国にあって初春の梅柳を賞する詩宴があった。奈良朝になってそれが和風化し、和歌の宴となっていたようだ。つまり、奈良朝においては、「花」といえば梅であった。平安朝になって花の代表の地位が梅から桜に移る。
なぜだろうと思って本棚を漁っていると、面白い文献を見つけた。『日本語の世界 11 詩の日本語』(大岡信 中央公論社)。簡単にまとめてみよう。
桜が「花」の代名詞の地位を得るのに重要な役割を果たしたものに「花の宴」がある。平安朝初期、嵯峨天皇が弘仁三年(812)春二月、神泉苑に行幸して「花樹を覧、文人(漢詩人たち)に命じて詩を賦さしめ」(『日本後紀』)たのが最初。
奈良朝では花の宴といえば初春(一月二十日前後)の梅柳を賞する詩宴と中国六朝伝来の曲水宴(三月三日)の二本立てであった。曲水宴というのは、寝殿造の庭園内にうねうねと屈曲させて作った小川に酒杯を流し、それが自分の前を流れすぎてしまわぬうちに詩を作り、杯をとって酒を飲む風流の遊び。この二つの宴が融合して嵯峨天皇のときに公式な花の宴となる。花の宴は同時に詩歌管弦舞踏の宴である。元々は1月に梅を賞した花の宴が、3月の曲水宴に移行したことで、公式な花の宴の主役は桜になり、詩歌管弦舞踏という当時の芸術の粋が桜を中心に展開することになった。
いつ、桜が花の代名詞として公式に認められたかという問いに対しては一応の答えが出た。だが、梅が桜に地位を譲ったからといって、「ああそうですか」と芸術の内容がその日から変わるほど事は単純ではない。それまで梅を最上の花として詠んでいた歌人たちが、桜をどのように詠めばいいのか。過渡期の作品として創作者たちの苦肉の策ともいえる作品群がある。日本文化の典型を考える場合、登場してもらわなければならない人物、紀貫之が主人公だ。
『土佐日記』の中に、「三月三日紀師匠曲水宴序」という題で、当代の代表歌人八名が集まって競作したものが記録されている。その中から、「花浮春水」という題の歌を引いてみる。
やみがくれ岩間を分て行水の声さへ花の香にぞしみける 躬恒
水の面に花はうきつつ行らめど香にこそめづれ色をやは見る 伊衝
山がくれ桜をぞ思ふ行く水に香さへなつかし瀬々のまにまに 友則
瀬々ごとにかけてぞ思ふちる花のうきて流るるかはみづの香は 興風
春の夜の更け行く水の香をかげばいづくともなく花こそありけれ 大江千里
何れをかいずれとわかん河浪のくさだつ花の香にまどはれて 坂上是則
岩そそぐ水に行きつつ花の香の空にめでたきやみがくれかな 壬生忠岑
春なれば梅に桜をこきまぜて流すみなせの河の香ぞする 紀貫之
八首とも、「香」が詠み込まれている。しかも、闇の中でも水の流れに花の香を感じ取るという感性は、中国の典型的な「暗香浮動」式の梅ぼめを下敷きにしている。しかし、旧暦三月三日といえば桜である。友則の歌には「桜」と明記している。紀貫之にいたっては「梅に桜をこきまぜて」とご丁寧にも香の強くない桜に梅の芳香をこきまぜるという無謀な試みまでがなされている。梅ほめは中国の正統を踏襲しておればいいが、桜は日本人がオリジナルに正統を作り出さなければならない。紀貫之にとってみれば、梅と桜をこきまぜてでも、何とか桜を正統に位置づけなければならなかったのだろう。その過渡期の苦労がこの歌からは感じることができて面白い。
なぜ他の花ではなく桜なのか
ここまでは、「桜の花がいつ日本文化の中心になったか」について考えた。そして、梅から桜への移行期の作品を紹介した。でも、まだ肝心の問いに答えていない。その問いとは、「なぜ他の花ではなく桜でなければならなかったのか」ということだ。
この問題を考えるにあたっても、『日本語の世界 11 詩の日本語』(大岡信 中央公論社)に全面的に依拠する。
典型の力というものは、僕たちの日常のものの見方を強力に支配する。この典型の力は文化という名前で置き換えてもいいだろう。僕は文化を次のように定義している。
「文化とは、ある集団の中において、無意識にまで習慣化された行動や思考の型であり、それによって作り出された有形無形の価値である」
奈良朝で花が梅を指すようになったのは、中国文化の影響下にあったからだ。それが、桜に変わったからといって、はいそうですかと服を着替えるように花に対するものの見方までも変えるわけにはいかない。梅から桜への移行期に、紀貫之は「梅に桜をこきまぜる」ような強引な方法によって桜を定着させようとした。この時期、梅ではしっくりこない何か、中国文化の影響を受けながらも、いやだからこそかえって日本独自のものを意識せざるをえなかった出来事があったのではないか。
歴史的にみると、10世紀が鍵になると思われる。花の宴が公式化されたのが嵯峨天皇の時代(812)だ。年代をさらっとおさらいしてみると、菅原道真が遣唐使の廃止を建議したのが894 年。紀貫之が日本最初の勅撰和歌集である「古今集」を編んだのが905年(914年という説も)。唐が衰退していく中で、遣唐使が廃止される。そして、中国文化という強力な文化のシャワーが途絶えた所で、それまで、中国文化の摂取に必死だったのが、それを消化吸収、あるいは選択排除という形で内面化するのに約一世紀かかったのだと考えられる。
遣唐使廃止を建議したのが菅原道真であるのは興味深い。なぜなら、菅原道真は無類の梅好きで知られているからだ。道真を祀った京都の北野天満宮や太宰府天満宮は今でも梅の名所だ。ちなみに僕が学生時代を送った拠点は、北野天満宮の近くの「北野白梅町」といいます。菅原道真が梅好きで有名であることが強調されるということは、その当時の中心がすでに桜であったことを意味している。彼は唐好みの代表者として、もう唐からは学ぶことはなしという自負があったのだろう。そして、そのことがその後の国風文化誕生のきっかけとなったという皮肉は、歴史を学ぶ醍醐味だといえる。
おそらく、桜が日本文化の典型になり得たのは、古今集の力によるものが大きい。古今集において日本的な美意識は最初の完成を見せるからだ。古今集というのは芸術家からは評判が悪い。正岡子規などはクソミソにこき下ろしている。確かに紋切り型というか、今の時代の僕たちからみると教科書的で面白くない。僕もずっと好きではなかった。でも、古今が典型を作ってくれなかったら、典型の破壊も生まれなかっただろう。そして、紀貫之が『土佐日記』を書かなかったら、ひらがなの地位は低いままでその後の女流文学は花開かなかったのではないか。この二点において、紀貫之は偉大な典型を作った言語改革者であった。その点は評価して評価しすぎることはないと思う。
最初の問いである「なぜ他の花ではなく桜なのか」について考えてみる。
桜の花の時期は、春の農事の開始の時期であった。花見とは「美を愛でる」という鑑賞的な意味だけではなく、より深く、日本人の農耕と結びついた儀式であったという見方がある。つまり、花見の遊山は田の神と神人飲食をともにする大切な行事であり、そこに桜の花を特別な意味も生じたという見方だ。大岡信は山本健吉の『最新俳句歳時記』(新年篇 文藝春秋)を引用して説明する。
桜の花が、稲の花の象徴と考えられ、その散り方如何が稲の花を予祝し、ひいては村の生活の全体の吉凶を占うものとされたからだ。花とは、元来前兆・先触れといをことで「ほ」「うら」という意味に近いものである。
自然との関係を生活の基軸に置いていた日本人の季節季節の節目におけるものの感じ方、そして森羅万象に神を見、神とともに飲み食い踊る日本人のアニミズム的感性をよくとらえた説明だと思う。自然の理をとらえ、言祝ぐのが詩の発生の起源であった。月や花というのは、そうした感性の象徴であり、また花の中でもとりわけ「桜」が選ばれたのも、日本という風土で生活して人々の自然との関わりがあったからだろう。だからこそ、桜を愛し、花見を楽しむ文化は、一部の芸術家や愛好家の独占物でなく、広く僕たちのような市井の人間にも愛されつづけてきた。
花の宴が公式化されて 1213 年目を迎える今年の花見は、日本人だけでなく、世界の人々も飲み食い踊れよかし。