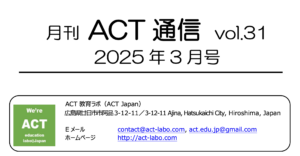海外生の「大学選び基礎講座」Road to U
第2回「Zero Hunger-2」
日本での大学進学を考えているけど、「大学でどんなことが学べるの?」「自分に向いている学部って?」と???でいっぱいのきみ、SDGsをヒントに自分のポテンシャルを掘りおこしていこう。自分に合った進路を見つけるためのレッスン「Road to U」、今回は経済学を切り口に他の学問分野も見てみることにする。きみのやりたいことが見つかるかな。
*Road toのUはuniversityのU
高校生に大学の志望学部を尋ねると、7〜8割が「経済学部」と答えるのではないだろうか。「なんとなくつぶしが効きそう(=就職に有利かも)」といったイメージ先行の理由もないとは言えないが、なんといっても経済学の扱う範囲は広い。どこかで必ず「自分の興味」につながる部分があることを考えると、むしろ当然かもしれない。
前回、『持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)』のゴール2”Zero Hunger”(飢餓をなくそう)へのアプローチから、データサイエンスと社会学を見てみたが、経済学もまた欠かせないプレーヤーであることは直感的にわかるだろう。
飢餓⇦食べ物がない⇦お金がない=経済の問題
単純な図式で言えば、そうなる。これを反転させるにはどうすればいいか。
(反転)経済の安定=お金がある⇨食べ物がある⇨飢えることがない=健康
経済の安定のためにできることはなんだろうか。この課題を開発途上国を対象に取り組むのが開発経済学だ。途上国援助と一口に言っても、その国の文化や歴史、政治、経済、人々のマインドを知らなくては役に立つアイデアは出せない。そのためもあって、経済学部だけではなく、国際関係学部や政治学部、法学部で開発経済学を学べる大学もある。開発経済学を選んだある先輩は、小学生のときに初めて親の仕事の都合で住んだ外国で自分と同い年ぐらいの子供が路上で暮らしている光景に衝撃を受け、そのことを考え続けた結果、志望学部が決まったと言っていた。
一方、じつは飢餓は遠い外国の話ではない。2024年のSDGs達成度レポートで、日本はGoal2の”Zero Hunger”に下向きの矢印がついていた。つまり食べ物へのアクセスが悪化しているのだ。そこまで生活に困っているのを実際に見たことがないという人も、子ども食堂については耳にしたことがあるだろう。子ども食堂の目的は、地域の子どもや家族を対象に無料または安く食事を提供するだけではなく、コミュニティのつながりを強くすることも大いにあるが、その数は2010年頃から増え続けている(現在約1万カ所)。飢餓とは縁遠い先進国のはずなのに何が起こっているのかをつきとめるには経済学の知見は欠かせない。
また、日本ではこの数ヶ月間、米の値段が上がり続け、現時点で去年の約2倍となっている。きみのお母さんやお父さんも「高い、高い」と最近ボヤいていないだろうか。米価が上がるとコンビニの弁当も米菓(せんべいとかおかきとか)も酒(料理にも使うよ!)も当然高くなる。流通の途中で誰かが値上げのために隠しているんじゃないか、いやインバウンドの観光客で消費が急に増えたせいだ、いやいや生産調整が行きすぎて収穫量自体が少なかったのだ、と様々な説が出ている。どれもありそうだが、なんとなくの印象に振り回されず、問題解決に取り組むには食料経済学の出番となる。この学問は食料の生産・流通・消費に関する経済学で、どう生産を安定させるかという点では農学部とも関連が深い。
飢餓の主な原因には、気候変動で引き起こされる自然災害や社会システムのゆがみから来る貧困、紛争、さらに大量のフードロスなどがあると言われている。気候変動に着目すると環境経済学の視点も欠かせないし、教育経済学は貧困状態から人々を抜け出させる手助けになるだろう。他にも◯◯経済学という学問は数限りなくある。「自分の興味」と結びつけて探してみると、ぴったりのものが見つかるかもしれない。