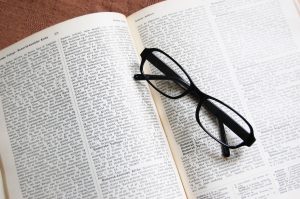あじなんだより Ajinan Report vol.30
ACT教育ラボの所在地は広島県西部にある廿日市市阿品(「はつかいちし・あじな」と読みます)。「あじな」の住民になった自らを「あじなん」と名づけ、暮らしの中で気づいたこと・感じたことを報告していきます。今回は日本語ボランティアとベトナム正月のあれこれ。Chúc mừng năm mới (チュックムン・ナンモイ:祝新年)!
今年は1月29日が旧正月の元日でしたね。マレーシアでは街中が真っ赤にそまって、「Gong Xi Fa Cai (恭喜發財)!」とアンパオのポチ袋やらミカンやらが飛び交ったのではないでしょうか。日本では特にこれといったイベントもなく何てことない平日ですが、ベトナムでも旧正月はテト(Tết)と呼ぶ、いちばんぐらいに大切な祝日だそう。毎週ボランティアの日本語教室で会っている我がベトナムグループの皆さんも、「お正月だしねー」ということで、レッスンは一回お休みとなりました。

ちょうど1年前、地元で日本語を教えるボランティアを始めたときから私が担当しているのがベトナム人のグエンさんとロックさん。牡蠣(かき)を扱う水産加工会社で技能実習生として働いています。同僚はほぼベトナム人とフィリピン人だそうで、広島の名産、牡蠣も彼ら外国人の仕事に支えられているのですね。
この週1回の二人クラス体制に11月からグエンさんの奥さん(出産のため本国に戻っていたが仕事に復帰)と職場の後輩ご夫妻が加わり、5人クラスになりました。グエンさん妻はNgânさんとおっしゃるのですが、この発音が難しい。お名前を聞いておきながら「XXXさんの奥さん」という呼び方はどうよと思う私としては名前で呼びたい、でもガンなんだかアンなんだか発音が定まらず、とりあえず口にして「だれのこと呼んだ?」みたいになっている状況も耐えがたく、つい「次はグ、、ア、Nga,はい、グエンさんの奥さん、どうぞ」と、日和ってどうする…。
で、彼らに聞いたベトナムのお正月のあれこれ。年末に大そうじをして買い出しに行く、というあたりは万国共通な感じがします。お寺などに初もうでに出かける、お年玉を配るのはアジアの共通項かな。

日本のお雑煮的に必ず食べるのは豚肉の入ったちまき、bánh chủng(バイン・チュン:左の写真)。マレーシアのketupat(クトゥパ:右の写真)に似てるので、手のひらサイズを想像していたのですが、今週たまたま見たNHKのテレビドラマで、これを食べるシーンがあり、サイズ感が違っていたことを発見しました。相当でかい。8個ぐらいに切り分けて食べるのが普通のようです。

我が学習者グループの皆さんは、「日本語試験のX級を取得して昇給を目指す!」とかの切実な目標ではなく、「日本語覚えて生活しやすくなったらいいかな」程度の軽めのモチベーションで、いわば趣味の語学。それだけに、きつい仕事の後によく勉強する気になるなあと感心します。こちらとしては、実用的な日本語をできるだけ楽しく身につけてもらうにはどうしたらいいか、腕の見せどころ(?)でもあります。とはいえ、もし日本語能力試験N5(入門レベル)が必要になったりしたときにあわてなくてすむよう、「男女」とか「左右」とか「上中下」とかの漢字も少しずつ導入中。皆さん、「うわ〜、かんじぃ〜」と抵抗されてます。そうでしょう、そうでしょう。私もベトナム語のアルファベットのằとかẫとかểとかẽとかỗとかọとかで、うわ〜っ、と叫んでおりますよ。