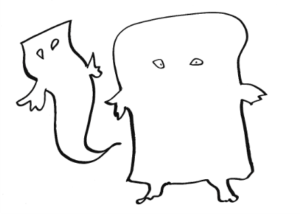さくぶん道場 第198回 大谷雅憲
特殊と普遍〜漱石と近代日本
今回は、漱石の『私の個人主義』をもとに「普遍と特殊」について考えてみたいと思います。
大学を卒業し、自分の中に空虚を抱えたまま教壇に立った漱石が、袋の中に閉じ込められて身動きできないような気持ちで煩悶をつづけます。30を過ぎてイギリス留学をしたときに、はじめて、袋を破る錐を見つける。漱石にとって、「袋を破る錐」、あるいは、「ここにあったぞ、と自らの内命の鉱脈を掘りあてたような気分になったツルハシ」とはなんだったのでしょう。彼は、それを自己本位の発見だといいます。
「たとえば、ある西洋人が甲という同じ西洋人の作物を評したのを読んだとすると、その評の当否はまるで考えずに、自分の腑におちようが落ちまいが、むやみにその評を触れ散らかすのです。つまり鵜呑みといってもよし、また機械的の知識といってもよし、到底わが所有とも血とも肉ともいわれない、よそよそしいものを我物顔に喋って歩くのです。しかるに時代が時代だから、またみんながそれを誉めるのです。」(「私の個人主義」夏目漱石 講談社学術文庫 )
このような状態を、漱石は「他人本位」と名づけます。このように西洋人の言うことに盲従して受け売りをしている英文学者としてのありかたが、漱石を空虚にするだけでなく、不愉快な煮え切らない思にとらえられます。
このような経緯があって、『文学論』という著作にかかります。「失敗の亡骸です。しかも畸形児の亡骸です。あるいは立派に建設されないうちに地震で倒された未成市街の廃墟なようなもの」と漱石自身が述べる『文学論』とはいったいどういった書物だったのでしょう。
「私は英文学を専攻する。その本場の批評家のいう所と私の考えと矛盾してはどうも普通の場合は気がひけることになる。そこでこうした矛盾が果たしてどこから出るかということを考えなければならなくなる。風俗、人情、習慣、遡っては国民の性格皆この矛盾の原因になっているに相違ない。それを、普通の学者は単に文学と科学とを混同して、甲の国民に気に入るものはきっと乙の国民の賞賛を得るにきまっている、そうした必然性が含まれていると誤認してかかる。そこが間違っているといわなければならない。たとい、この矛盾を融和することが不可能にしても、それを説明することはできるはずだ。そうして、単にその説明だけでも、日本の文壇は一道の光明を投げ与えることができる。──こう私はその時はじめて悟ったのでした。」(「私の個人主義」同上)
「科学と文学を混同している」という部分に注目してみましょう。科学はどこの国、どの宗教、どの文化であっても「1+1=2」という世界で成立しています。これは別の言葉でいうと、科学は普遍的な真理であるということです。近代科学は西洋で生まれました。だから、西洋人は、自らの科学技術だけでなく、それを生み出した自分たちの価値観、政治形態、文化も同時に普遍的なものとして考えていたはずです。社会進化はらせん状に発展していき、その最先端にいるのが、西洋で、他の国はその発展段階に達しない後進社会であり、それぞれの特殊性に邪魔されている。
西洋の自己意識だけでなく、当時の日本人もそう思ったはずです。自分たちの発想や文化は特殊であると。だから、科学技術だけでなく、政治形態や文化や、文学までも普遍に近づく必要があると考えた。その結果、英文学が自分たちにとってピンとこなくても、理解しようとし、理解したふりをし、鵜呑みをしてしまう。他人本位とはそういう状態のことを指します。しかし、そうやって鵜呑みにしてきたものは、自らの血肉になっていないので、どこか空虚な感じを持たざるを得ない。それが漱石の煩悶を生み出す。
漱石はどうしたか。「文芸に対する自己の立脚地を固めるため、固めるというより新しく建設するために、文芸とは全く縁のない書物を読み始め」ます。文学を研究するために、科学や哲学を研究するわけです。当時漱石がやっていたことは、日本人のみならず、イギリス人にだって理解できなかったと思います。イギリス人にとって英文学とは、所与のもの、つまり、疑問を持つ必要のない自然なものです。だから、あらためて文学とは何かという問を立てる必要がなかった。
では、「文芸に対する自己の立脚地」とは何でしょう。それは、簡単にいうと、「日本文学が特殊であるように、英文学もまた特殊(ローカル)な文学である」ということです。誰もが普遍なものとして疑わなかった西洋世界の普遍性を、特殊(ローカル)なものとして見なすためには、その底にもう一つの地殻を見つけなければなりません。これが、漱石が掘りあてたと感じた鉱脈です。相対化という言葉の正しい意味を漱石はすでに発見していたことに驚きます。
おそらく漱石の『文学論』は世に出るのが早すぎました。彼自身の力量だけでなく、時代も人も彼の意図をすら理解できなかったのではないかと思われます。それでも、そのような「失敗の亡骸」が、日本の文学史上にあるというだけで、何か誇らしい気がするのです。