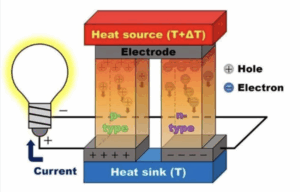さくぶん道場 第197回 大谷雅憲
言葉と文化
「言語と文化は、離れがたく密接な関係にあり、バイリンガルということはバイカルチュラルであると言われていますが、あなたは同意しますか。考えるところを述べなさい。」(03年 国際バカロレア 日本語上級レベル問題)
僕たち日本人は、当然のように日本語を使っている。日本で生活していると、「日本語を使ってコミュニケーションしている」ということすら意識することはないだろう。だが、内からの自然な言葉の変化とは別に、外国語の大量移入によって、日本語は二度、その構造自体を変化させてきた。最初は中国語、次が明治期の欧米語の影響を受けながら。
「日本語」は明治時代に作られた
明治期の日本は、ヨーロッパをモデルに急激な近代化を達成していく時期だった。それは同時に「諸藩連合国家」であったそれまでの日本が「大日本帝国」という国民国家に脱皮する時期でもあった。それを実現するために、「日本語」という標準言語を作り出し、「私たちは日本人である」という意識を作り出す必要があった。
この時期、どれぐらい日本語に変化があったかを示す例として、J.C.ヘボンが編纂した『和英語林集成』という辞書の収録語数を見てみよう。慶應3年に刊行された初版では総語数が2万722語だったのが、明治19年の第3版では3万5618語になり、20年で約1万5000語増加している。その理由として、「明治維新以後の日本語の変化発展は目覚ましいものであった。あらゆる分野でことばが増加した。そして、増加したことばの大部分は漢語であった」と、第3版の序文でヘボンは述べている。当時の日本人が漢字の造語能力を利用して、欧米語の翻訳語として次々に日本語を作っていったことがわかる。
「私の頭は半分西洋で、半分は日本だ」
「西洋の衝撃」を受けて変化したのは単語のレベルだけではない。夏目漱石の次のメモを見てみよう。
A若イ男ノdescription其 motive straight 凡テノ物ヲ destroyスル in the way destroy出来ヌ時ハstand still
B「トラセンデンタル、カーヴで出来上がつている。到底普通のフアンクシヨンではあらはせないサーフエスだ」「キユラソー」ノ瓶と青羊羹とはコンプレメンタリー、カラー
1905・6年に書かれたこのメモは、漱石の内的言語だと言える。彼の頭の中は、このような言語で思考されていた。漱石は、「将来の文章」で次のように言う。
「私の頭は半分西洋で、半分は日本だ。そこで西洋の思想で考えた事がどうしても充分の日本語では書き現されない。(中略)反対に日本の思想で考えた事はまた充分西洋の語で書けない。」
もちろんメモのような文章では他人に自分の考えを伝えることはできない。二つの言語に引き裂かれた漱石の内的思考を統一して、世間に通用する「国民語」を創造すること。漱石は優れた文学を創造すると同時に現代日本語を作り出すという困難な事業にチャレンジした現代日本語のパイオニアだった。
次に文章のスタイルに目を向けてみよう。一つの表現を手に入れるということは、一つの物の見方、考え方を手に入れることに等しい。例えば、「なぜ?」と聞かれたら「なぜなら、~から。」と答える形式は、英語の「Why? Because,.......」の翻訳だ。新しい日本語の文章=新しい思考・表現方式を考える漱石は、こうした翻訳体の表現を積極的に取り入れた。例えば、「吾輩を写生しつつある」の進行形、「十分寝た」の“enough”の翻訳語、「吾輩は猫として決して上乗の出来ではない」の“as”の翻訳語。「勇気はないと云はんばかりの顔」の仮定表現。「今まで世間から存在を認められなかった主人」の受身の表現等々。例を挙げればきりがない。
現代日本語の原型は「夏目漱石型文体」
漱石は英語の表現の方法を取り入れることで、日本語での思考・表現の世界を格段に広げた。もちろん一人の人間が一つの言語のありかた全てを変えることはできない。しかし、「夏目漱石型の文体」が基本の型となったことだけは確かなようだ。そして、この「夏目漱石型の文体」は先ほどのメモからわかるように、英語=イギリス文化との徹底的な格闘の中で生まれたものであることを忘れてはならない。
バイリンガルがバイカルチュラルであることの典型的な例を夏目漱石を通して見てきた。これから、日本語はどのように変化していくのだろうか。日本語の海から離れた環境にいる君たちだからこそ、日本語の現在に敏感になって欲しいと思う。いつの時代でも、異なる文化がぶつかり合った場所にいる人間が新たな文化創造の主体になるのだから。