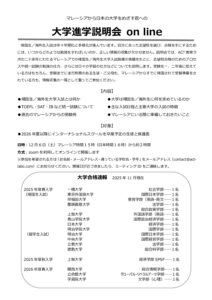あじなんだより Ajinan Report vol.34
ACT教育ラボの所在地は広島県西部にある廿日市市阿品(「はつかいちし・あじな」と読みます)。「あじな」の住民になった自らを「あじなん」と名づけ、暮らしの中で気づいたこと・感じたことを報告していきます。今回は、五月に出かけた瀬戸内海の島への小旅行を回想しつつ。ま、天気が良ければどこでも楽しいんですよね。
五月晴れのある日、「思い立ったが吉日!」の日帰りドライブで愛媛県の大三島(おおみしま)に行ってきました。早朝、廿日市を発ってひたすら東進し、三原市へ。ここからフェリーで島に向かうルートにも惹かれましたが今回は尾道まで走り、しまなみ海道で島づたいに大三島に向かうプランにしました。
大三島には大山祇(おおやまづみ)神社という、立派なお社があり、大山積命(オオヤマヅミノミコト)がまつられています。神社のロケーションからして航海の安全とか海の豊穣を願う、海専門の神様だと思っていたのですが、古事記等では「おおやま(・・・・)づみ」だけに山々を守る神様とあるそうで、なんだか謎です。


昔、中学か高校かの国語の教科書で、この神社の境内にある樹齢二千六百年のクスノキの話を読んだ記憶があるのですが、出典が何だったのかが未だもって不明。どなたかご存知の方いらっしゃったらご教示ください。
ここの宝物館には昔の刀剣やら甲冑やらが展示されていて、趣味の人にはたまらない魅力がありそうです。私は全く造詣が深くないので「へー」とか「ほー」とか言いながら眺めるだけですが、元寇の際のモンゴル軍の鉄カブトにはなんだかしみじみきました(モンゴル語学科卒でございます)。でも、じつはこのときのモンゴル軍って主に朝鮮半島の人たちで構成されてたんですよね。そりゃそうだわ、海なし国のモンゴル人が船に乗って玄界灘を越えるのはムリだもんね(と偏見に満ちた考察を加えてみました)。
このあたりの瀬戸内海の島々は昔はミカンの生産が盛んでした。子供の頃、島の農家にミカン狩りにおじゃましたことがありますが、当時すでに農家の高齢化が進んでいて、島の狭い土地を耕して作った段々畑を行き来するのは相当な重労働。「もうミカンは無理じゃのう」なんて、当主のおばあさんがおっしゃっていたことを思い出します。

そのまま柑橘産業が廃れるのかと思いきや、今は広島県がレモン生産量第1位を誇っており、愛媛はそれに次ぐ第2位。ミカンが昔ほど手頃でなくなったのは残念ですが、農薬の少ないレモンが手に入りやすいのはうれしい限りです。大三島の道の駅でもお買い得なレモンがどっさり売っていて、手当たり次第に買ってしまいました。で、うちに戻って作ったのがこのレモンジャム。さわやかな酸味で上出来じゃ〜と自画自賛しています。