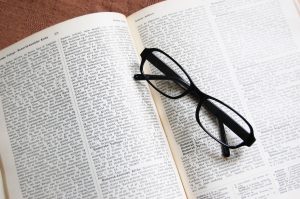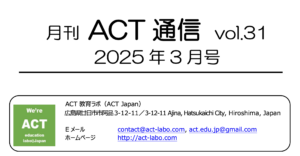海外生の「大学選び基礎講座」Road to U
第1回「Zero Hunger−1」
日本での大学進学を考えているけど、「大学でどんなことが学べるの?」「自分に向いている学部って?」と???でいっぱいのきみ、SDGsをヒントに自分のポテンシャルを掘りおこしていこう。自分に合った進路を見つけるためのレッスン「Road to U」、スタート。
*Road toのUはuniversityのU
『持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)』は 2015年にその先15年間の目標として国連で採択されたが、今年はすでに2025年。2030年まで、あと5年しか残っていない。昨年の公式レポートによると日本の成績は世界18位とはいえ、達成できている(緑色)のは一つ、ゴール9(産業と技術革新の基盤を作ろう)のみ。残りの課題は下の図表の通り。
https://dashboards.sdgindex.org/profiles
SDGsの中で、きみが気になるのはどれだろう? なぜそのゴールに興味をひかれるのか、これまでの経験をもとに考えてみてほしい。それが自分に合った進路を見つける第一歩だ。この17のゴールをよく見ると、それぞれが関連していて、じつは全体がつながっていることがわかると思う。そのどこに注目をするかにきみの個性が現れる。(日本の達成度 2024年↓)

今回はゴール2のZero Hunger(飢餓をなくそう)へのアプローチで考えてみよう。世界には十分な食べ物を得られない人が8億人以上いる。じゃあどうするんだ、毎日おいしくご飯を食べている自分(と豊かな生活を送っている人々)がガマンすればいいのか?! と結論を急いではいけない。世界中のトップ・オブ・ザ・トップの頭脳が長年かかって探しつづけている解決策をここできみに出せなんて無茶は言わない。というか、その答えを探すためにも大学で学んでほしいと思う。もし、きみがこのZero Hungerに取り組むタスクフォースに加わるとしたら、どんな分野で才能を発揮したいだろうか。
まずはデータの収集・分析部門。世界のどんな場所でどんな人たちが食べ物に困っているのかがわからなくては、次のステップには進めない。そこで活躍するのがデータサイエンティストだ。データサイエンスは統計学と情報工学を横断する比較的新しい学問で、ざっくり言えばIT技術を使ってビッグデータを処理し、統計学をベースに分析を行う。お店の売り上げアップから地球環境の未来予測にまで役立つ、このオールラウンドな技術なしに今後どんな分野の研究も成り立たないと言われている。そのため、日本国内でデータサイエンスを学べる学部・学科はどんどん増えていて、例えば早稲田大学では文系・理系関係なく、どんな学部の学生でもデータサイエンスを基礎から学べるプログラムを提供している。
データサイエンスは、この早稲田大学の例からも分かるように、ゴリゴリの理数系の人でなくても学ぶことができる。とはいえ、ある程度の数学センスは必要で、自分でプログラムを書いて、それがきちんと動いた時によろこびを感じるようなじるようなタイプなら進路の候補に入るだろう。
データサイエンス学部のある大学で帰国生入試を行なっている国公立大学の一つに横浜市立大学がある。この大学もそうだが、国公立・私立とも、情報工学系や理工系の学部ではSATのスコア提出を求められる(IB、A-levelの資格者以外)ことが多いので、その点のチェックを忘れずに。筑波大学の情報学群では、日本の学校に通算4年以上通ったことがない学生は留学生と同じ扱いとなり、日本留学試験(EJU)が必須となる。
*日本留学試験(EJU)は年2回(①6月と②11月)に行われる日本の大学に入学するための筆記試験。出願時期は①が2月~3月始め、②が7月。日本語・理科(物理・化学・生物)・数学・総合の中から志望校が指定する科目と出題言語(日本語または英語)で受験する。マレーシアではKLのSunway Universityが会場になっている。
データの収集・分析と同じぐらい大切なのは現地でのリサーチだ。数字だけではわからない、その場所の人々の暮らしや考え方をインタビューやアンケート、観察、資料収集などを通して理解するためには、フィールドワークを得意とする社会学が役にたつ。人々は何を食べて(または食べないで)どんな場所で寝起きしているのか、どんなことを考えながら生活しているのか等々、好奇心と現場に飛び込んでいく行動力がものを言う学問だ。
社会学がカバーする範囲はやたらと広く、人間と社会に関することなら何でも研究対象になる。例えば、「ノラねこのいる社会といない社会の比較」なんて研究も大まじめに行われている(ただし、この研究リーダーは経済史の専門家)。そういう意味では、やりたいことがしぼりきれていない人に向いているとも言える。
一橋大学・社会学部の帰国生入試は「外国学校出身者選抜」という名称になったが、出願資格・試験科目は以前と同じく、日本語小論文と英語のテストと面接。日本語でものを考える習慣があれば目指す価値はある。また、早稲田大学の社会科学部も帰国生入試をやめて「外国学生のための学部入試」に統一した。こちらは日本国籍を持っていてもEJUの成績が求められる。ただし、同学部の英語学位コースTAISIはグローバル入試で、学校の成績とTOEFL等の スコア、英文志望理由書を出願時に提出することになる(2027年入学からカナダ系インター校生はSATが必要)。(続)
帰国生入試・グローバル入試・AO入試(基本型:例外あり)
*帰国生入試は英語の外部試験(TOEFL、IELTSなど)のスコアと受験会場で行われる日本語小論文・面接(理系学部では日本語での筆記試験がある場合も)の試験で合否が決まり、一般学生と同じ4月入学となる。
*グローバル入試は学校の成績(IB、A-levelなどの見込み成績)またはSATのスコア、英語の外部試験、英文志望理由書の書類審査で合否が決まり、ほとんどが秋入学。卒業まで英語のみで学位が取れるコースの募集でよく行われる。
*AO入試 大学ごとに独自の方式を課す。上記2つをミックスしたものが多い。